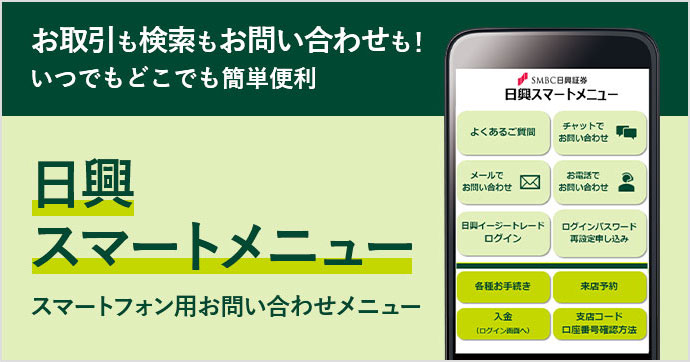相続・相続税に関する基礎知識
相続対策をはじめる前に、事前に知っていただきたい「相続・相続税」に関する知識です。
相続に関する基礎知識
相続人になる人
相続が発生した際、財産を引継ぐ人を法定相続人(以下、相続人)といいます。
相続人になる人は、民法に定められています。
なお、相続人ではない人に財産をあげたい場合には、生前に遺言を作成したり、贈与したりすることが必要となります。

- 【子が既に亡くなっている場合】
- 相続人となるはずであった子が、亡くなられた方より先に亡くなっている場合には、孫やひ孫が代わりに相続人となります。これを代襲相続といい、その相続人のことを代襲相続人といいます。
相続財産分割の流れ
相続財産を分割する際、遺言書がある場合には、原則として、遺言の内容にしたがって分割します。一方、遺言書がない場合には、相続人全員の話合い(遺産分割協議)により、分割方法を決定し、分割します。

遺言の内容にしたがって分割します。
- ※ただし、相続人全員の合意により、遺言とは異なる分割を行うことも可能です。
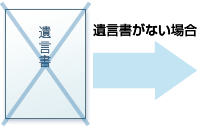
相続人全員の話合いにより、分割方法を決定します。
これを遺産分割協議といいます。
相続人全員が合意した内容に基づき、分割します。
- 【遺産分割は法定相続分どおりに分割しなければならない?】
- 相続人が取得する財産の割合は、民法に規定(=法定相続分)がありますが、実際の遺産分割の際は、必ずしも法定相続分にしたがって分割する必要はありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割も可能となります。
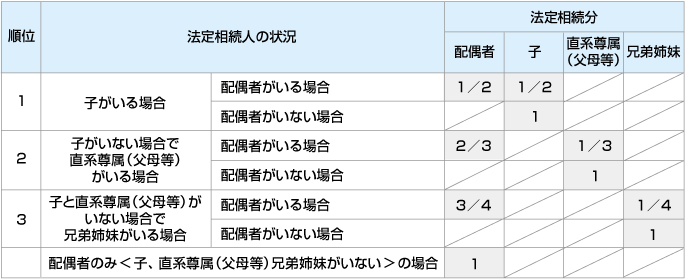
相続税に関する基礎知識
相続税が課税されるケース
相続税は、純遺産額が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合に、原則として、課税されます。なお、ここでいう『純遺産額』とは、相続や遺贈により取得した財産(生命保険金等の「みなし相続財産」を含みます)に、「暦年課税において被相続人から加算対象期間内に贈与を受けた財産※1」、「相続時精算課税制度を選択した贈与財産※2」を加算し、債務や葬式費用を控除した後の金額をいいます(以下同じ)。
- ※1加算対象期間は被相続人の相続開始日が2026年までは、相続開始前3年以内ですが、2027年から順次延長され、2031年以後は相続開始前7年以内となります。
延長された4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産には加算しません。 - ※22024年1月以降の贈与から毎年110万円の基礎控除が創設され、基礎控除分の贈与財産額は相続財産に加算されません。
純遺産額 > 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
ただし、純遺産額が基礎控除額を超える場合でも、未成年者控除や障害者控除等の各種控除の適用により、課税されないこともあります。
また、相続税の特例を適用することにより、相続税が課税されないで済むこともあります。
代表的な相続税の特例には、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」があります。
相続税・贈与税の内容
相続税および贈与税の主な内容は以下のとおりです。
(各項目の「 + 」ボタンをクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。)
相続税の主な内容
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄をした人も含みます。
また、税法上、法定相続人に含められる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
| 法定相続人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
相続税額は「各法定相続人の取得金額×税率−控除額」で計算します。
税率は8段階あり、最高税率は55%となっています。
| 法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 1,000万円超 〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与税の主な内容
贈与税は「暦年課税制度」または「相続時精算課税制度」により計算します。
暦年課税の場合、「(贈与を受けた金額(年間合計)−基礎控除額110万円)×税率−控除額」で計算します。
「18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与」と「それ以外の贈与」で税率構造は異なります。
| 【特例税率】18歳以上の者が 直系尊属から受けた贈与 |
【一般税率】左記以外の贈与 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
| 400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超〜 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | ||
相続時精算課税制度は、要件を満たした60歳以上の親および祖父母から18歳以上の子および孫への贈与において、贈与財産額が2,500万円まで贈与税が課税されない制度です。贈与財産は、贈与者に相続が発生した際の相続財産に加算され、相続税で精算されます。
なお、特別控除額2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税が課税されます。この時支払った贈与税は相続税額より差し引くことができます。
2024年以後、相続時精算課税制度においても暦年課税とは別途110万円の基礎控除が新設されます。基礎控除分の贈与財産の価額は相続財産に加算されません。
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!

各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。

免責事項
当ページのいかなる内容も将来の運用成果、市場環境の変動等を示唆、保証するものではありません。
当ページの掲載資料および内容は作成時点の法令、その他情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合等があり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性についてSMBC日興証券が保証するものではありません。
当ページの内容にかかわらず、お取引に伴う税制の適用はお客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。
当ページの内容はSMBC日興証券が有価証券の売買その他取引等を誘引する又は投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
当ページに掲載の動画、静止画、記事等の情報は、収録時点のものであり、その後、変更されている場合があります。最新の情報は、ご自身でご確認ください。
コンテンツの内容に対する改変、修正、追加等の一切の行為を禁止いたします。
- ※本資料は2023年11月1日現在の法令その他の情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合があります。