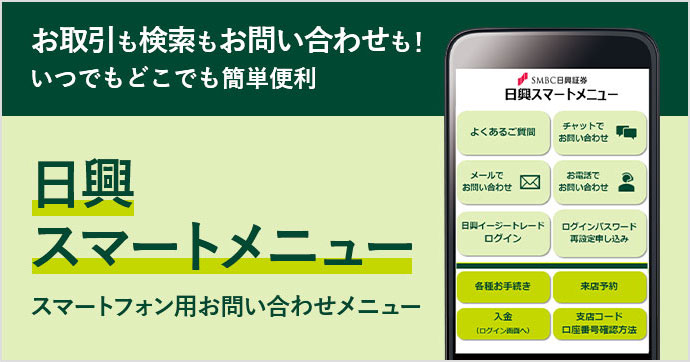FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」【第18回】
【第18回】贈与したのに贈与ではない!?
2015年9月17日
FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」では、毎月1回、相続に関連したお役立ち情報から最新の話題までをお伝えしております。第18回目のコラムは、贈与に関する留意点のお話です。
贈与をされる方は年々増加傾向
贈与税の申告をされる方の人数は年々増加しています。本年1月より相続税が改正され増税となったことから、相続税対策として有効な贈与を利用される方が増えているからではないでしょうか。そこで、今回は贈与を行う際の留意点についてご説明します。
| 2014年分 | 519 |
|---|---|
| 2013年分 | 491 |
| 2012年分 | 437 |
| 2011年分 | 427 |
| 2010年分 | 395 |
贈与は「あげる方=贈与者」と「もらう方=受贈者」の契約
表題の通り、贈与は「贈与者」と「受贈者」の契約です。この契約は口頭でも書面でもどちらでも行うことができます。ただし、契約だけで贈与が成立するかというとそうではなく、実際に財産移転が履行されたことによって成立します。そして、贈与履行後、贈与財産は「受贈者」の所有物となることから、当然その財産の管理は「受贈者」が行うことになります。例えば贈与者が受贈者の銀行口座に振込むのであれば、その口座の通帳と印鑑を受贈者が管理することになります。
- ※祖父母世代から孫世代に対する贈与を行う際、「受贈者」が未成年であれば、親権者である父・母が未成年者に代わってこれらの契約・管理を行うのが一般的です。
贈与したと思っているけど、贈与ではない!?
ところが、実際にはこれらのことが行われていないことがよくあります。
たとえば、お子様やお孫様名義の口座に、お子様やお孫様には秘密にしておきながら財産を移していくようなケースです。この場合、秘密にしているということは、お子様やお孫様は財産移転を認識していないことになりますので、「贈与者」と「受贈者」の契約があったとはいえません。
また、契約はしつつも、贈与財産を引き続き「贈与者」が管理しているようなケースもあります。「贈与者」が引き続き管理しているということは、「贈与者」がいつでもその財産を処分できることになってしまいます。贈与した財産は「受贈者」の所有物で「受贈者」の意思で処分できるはずのものなのに、これでは矛盾が生じてしまいます。
『贈与ではない』とされるとどうなるのか
上記のようなケースに該当すると、口座名義人はお子様やお孫様であっても実質的には「贈与者」が所有者であるとされる可能性があります。そして、その場合には「贈与者」の相続発生時における相続税の課税対象となってしまいます。
また、本年9月3日には「改正マイナンバー法案」が可決成立しました。これにより、2018年からは預金者の「任意」で預金口座とマイナンバーが紐付けられるようになります。今回成立した内容はあくまでも「任意」という形で決まりましたが、将来的には「義務」となる可能性もあるのかもしれません。もしそうなった場合には、上記のような口座は誰のものなのか問題になることも考えられます。
贈与のポイント
相続税対策として行った贈与が贈与ではないとされてしまうと、結局は相続税対策とはならなくなってしまいます。贈与を行った後に、誰の財産なのかといった問題を生じさせないためにも、贈与の契約については書面で行い、贈与契約書という形で記録を残しておき、贈与後の財産管理については受贈者が管理することが大切です。
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!

各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。

免責事項
当ページのいかなる内容も将来の運用成果、市場環境の変動等を示唆、保証するものではありません。
当ページの掲載資料および内容は作成時点の法令、その他情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合等があり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性についてSMBC日興証券が保証するものではありません。
当ページの内容にかかわらず、お取引に伴う税制の適用はお客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。
当ページの内容はSMBC日興証券が有価証券の売買その他取引等を誘引する又は投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
当ページに掲載の動画、静止画、記事等の情報は、収録時点のものであり、その後、変更されている場合があります。最新の情報は、ご自身でご確認ください。
コンテンツの内容に対する改変、修正、追加等の一切の行為を禁止いたします。