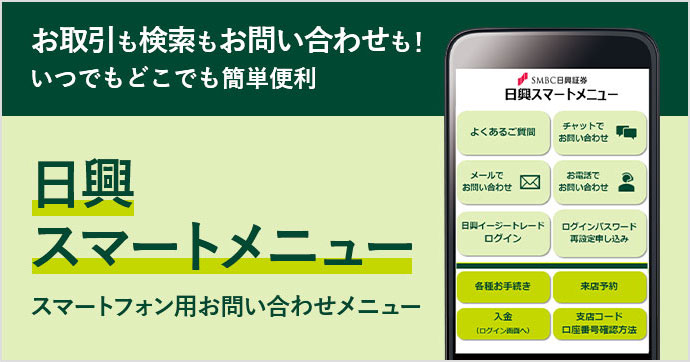FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」【第76回】
【第76回】2025年問題から2040年問題へ、対策や準備は?
2025年3月31日
FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」では、相続に関連したお役立ち情報から最新の話題までをお伝えいたします。第76回目のコラムは2025年問題から2040年問題に向けて行うべき対策や準備に関するお話です。
2025年、2040年問題とは?

「2025年問題」「2040年問題」という言葉をご存じでしょうか?「2025年問題」は団塊の世代(1947年〜1949年生まれ)が全員75歳以上になることで、日本の約5人に1人、2,180万人が後期高齢者となり、社会保障や医療・介護の負担が増加する一方で、働き手不足や後継者不足が顕在化する問題を指します。
次に予想されている問題が「2040年問題」です。団塊ジュニア世代(1971〜1974年生まれ)が65歳以上となり、国民の約3人に1人に相当する3,920万人が高齢者になります。高齢者人口がピークに達する一方で、生産年齢人口が減少し、1.5人の現役世代で1人の高齢者を支える状況となり、経済や社会の維持が危機的になると予測されています。
国の対策・個人の対策
国は上記問題に対応するため医療・介護費の負担割合変更や介護職員の待遇改善、外国人労働者の受入れ、女性や高齢者の就業促進などの対策を進めていますが、社会保障制度の見直しには多額の財源が必要になりますし、言語や文化の違いから外国人労働者の確保も難しい状況です。
では、個人でできる対策にはどのようなものがあるでしょうか?まず、健康を維持することが重要です。一人ひとりが定期的な健康診断や運動により、健康を維持することができれば、医療・介護費といった社会保障制度の負担増加を抑えることができますし、健康であれば高齢であっても働き続けることが可能になるので、働き手不足問題の軽減も期待できます。次に、経済的な備えも必要です。高齢になると健康に気を付けていても体調不良のリスクが高まるため、医療・介護費の増加に備えて資産を計画的に管理することが求められると思います。
大相続時代
さて、上記問題は相続にも大きな影響を及ぼします。まず最初に高齢者が急増するため相続発生件数も増加し、現在の年間160万件から、2040年には年間170万件に達する可能性もあると予測されています。これに伴い①遺産分割協議で親族間の意見が対立するなど相続関連のトラブル件数の増加※1、②相続による空き家増加に伴う環境の悪化、不動産市場への影響、地方都市の衰退、都市圏の高齢化※2、③地価や株価が上昇したことによる相続税の課税対象件数の増加及び相続税の家計への負担増加※3が予見されています。
さらに、相続人自身も高齢である可能性も高まっています。そのため相続人の体力や判断能力が低下して、認知症を患っている等、相続手続きがスムーズに進まない可能性や高齢者の増加、家族関係の多様化により、相続人の構成も多様化することが予想されます。子どもがいないため兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースが増え、相続手続きが複雑化することも懸念されています。
- ※1家庭裁判所へ持ち込まれる遺産分割争いの案件はここ20年で1.5倍に増加
- ※2空き家率は、2023年の13.8%から2043年には約25%に増加の見通し
- ※3相続税課税割合は、2014年の4.4%から2023年には9.9%に増加
遺言書の作成を検討する
「大相続時代」におけるトラブルを防ぐために有効な対策の一つが、「遺言書の作成」です。遺言書を作成することで、遺産分割協議を行う必要がなくなり、親族間の争いを軽減することができますし、空き家問題についても所有権を明確にすることで相続後の管理や処分に関するトラブルを避けることができます。さらに相続人に認知症の方がいる場合でも、複雑な手続きを行うことなくスムーズに相続手続きを進めることが可能になります。そして何よりも、遺言書を通じて自分の想いや考えを明確に遺すことが可能になります。
生前贈与を検討する
「2025年、2040年問題」、「大相続時代」共通して重要なことは、資産を守るということです。医療・介護費の支出に備えるだけでなく、今後の社会保障制度の負担増加や増税傾向に対処しながら、ご自身の資産を次世代に引継ぐことが必要になります。そのための有効な対策が、「生前贈与」です。生前贈与を活用することで、贈与をする人が自らの意思で、好きなタイミングで資産を子や孫といった次世代に渡すことが可能になります。さらに贈与税の非課税枠を利用しながら資産を早めに移転することで、相続税の負担軽減にもつなげることも可能になります。
2025年問題から2040年問題へ
これまで「2025年、2040年問題」について触れてきましたが、現在私たちが直面している「2025年問題」は、今後の問題の始まりに過ぎないことが分かっていただけたと思います。次に予想されている「2040年問題」まで考えても残された時間はあまり長くありません。有効な対策としてご紹介した「生前贈与(暦年課税)」も富の再分配、税制の中立性、国際的な動向等の観点から2024年1月1日以降の贈与について相続税の加算期間が3年から順次7年に変更されるなど増税傾向の変更が行われています。
今後ますます増えるであろう増税施策から資産を守り、次世代に無事に引き継ぐために、ぜひ一度ご自身の資産を見直してみてください。そして、ご家族で話し合う機会を持つことをおすすめします。
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!

各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。

免責事項
当ページのいかなる内容も将来の運用成果、市場環境の変動等を示唆、保証するものではありません。
当ページの掲載資料および内容は作成時点の法令、その他情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合等があり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性についてSMBC日興証券が保証するものではありません。
当ページの内容にかかわらず、お取引に伴う税制の適用はお客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。
当ページの内容はSMBC日興証券が有価証券の売買その他取引等を誘引する又は投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
当ページに掲載の動画、静止画、記事等の情報は、収録時点のものであり、その後、変更されている場合があります。最新の情報は、ご自身でご確認ください。
コンテンツの内容に対する改変、修正、追加等の一切の行為を禁止いたします。